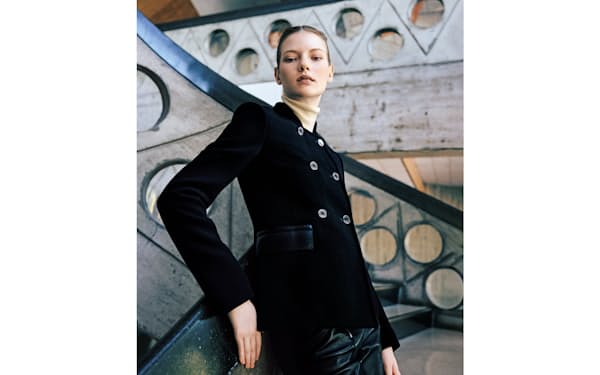「育ててこそ」の気概を、日本サッカーにもう一度(田嶋幸三)

短い下り坂の時期はあったにしても、日本サッカーの競技レベルはこの数十年で右肩上がりの曲線を描いてきた。それはひとえに、私たちサッカー人が選手育成をおろそかにしなかったからだと思っている。
日本サッカー協会(JFA)の育成事業に長らくかかわってきた私の経験上、選手が偶然に育つことはありえない。子どもの個性は大人が見いだし、導き、頭角を現せば階段を一つ上らせる。この果てしない営為が日本サッカーを豊かにしてきた。だが先々を見こすと気がかりなことがある。このところ「育ててこそ」の気概が薄らいでいる気がするのだ。
育成年代の日本代表が海外遠征に出向く機会が減っている。これはJFAの収益構造がこの数十年で変化したことも絡んでいて、仕方がない面もある。
サッカーバブルに沸いた1990年代の前半は、2002年ワールドカップ(W杯)招致のためにJリーグや開催候補地からいただいた資金を、若い世代の強化費に割くことができた。目的は02年大会で代表チームの中心を担う選手を育てることだった。国境を越え、異国のライバルたちと手合わせを重ねた体験は中田英寿、中村俊輔、小野伸二ら、のちにゴールデンエージと呼ばれる選手たちを大きく成長させた。
いまは時代が違って、あの頃のように強力なテコ入れは望めない。金銭面の話にとどまらず、昨今は各年代の代表チーム編成が難しくなっている。代表監督が選手を呼ぼうとしても「大事な試合があるので」とクラブや学校の指導者に苦い顔をされることがある。これは中学生、高校生の2世代でリーグ戦を整えてきたJFAの成果と裏腹の、思いがけない副作用なのかもしれない。
例えば、高校世代には「高円宮杯 JFA U-18(18歳以下)プレミアリーグ」というトップリーグがあって、Jクラブのユースチームと高体連の強豪校を合わせて全国24チームが東西に分かれてしのぎを削っている。さらにまた、下部リーグとして「高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ」という鍛錬の場が全国9地域に用意されている。
リーグ戦のメリットは同レベルのチーム同士が競い合えること。この日常を獲得できたのは喜ばしいが、それとは別に、日の丸を背負った試合でしか養えないものがある。日本代表の体験はやはり何ものにも代えがたい。
コーチたちはおそらく、目の前の試合で勝つことを諸方面から求められているのだろう。だが育成年代の選手をあずかるコーチの評価軸は「どれだけ勝ったか」ではなく「誰を育てたか」であるべきだ。掌中の玉を一段と輝かせるために代表チームに送り出す、あるいは次のステージへ〝飛び級〟させることに、どうかコーチのみなさんは思いを致していただきたい。
海の向こうには、バルセロナの18歳ラミン・ヤマルのように10代で活躍するタレントがぞろぞろいる。この動きにキャッチアップしたい。17歳でプロデビューを飾り、W杯に2度、3度出場する選手が次々と出てくるようでなければ、日本はW杯優勝を毎度狙えるようなサッカー大国になりえないと思う。

Jクラブにもお願いしたいことがある。ユースの選手から月謝をもらうのをやめにして、高校生になったらプロ契約を結んで給料を払ってはどうだろうか。
せっかく育ててトップチームに昇格させた選手が、すぐに渡欧してしまう時代である。数億円の移籍金をもらっても引き合わない、下部組織の運営費は安くすませたい、という気持ちはわかる。だが欧州の青田買いはさらに進んで、いまやプロデビュー前の高校生に誘いの手が伸びている。
自クラブのユース選手であっても、契約前にさらわれると移籍金というプロテクトが働かず、数千万円の育成補償金という〝涙金〟が手元に残るだけ。それなら、早くに複数年契約を結んで当人にプロの自覚を持たせたほうがいい。
Jリーグには40人近い選手を抱えるクラブがあるが、けが人の穴埋めにシーズン半ばの〝中途採用〟を増やすくらいなら、ユースの有望株を昇格させたほうが経済的だろう。どんどん試合に使って商品価値を上げ、欧州から買い注文が入れば移籍金を下部組織に再投資。そのほうが、晩稲(おくて)より早稲(わせ)に高い値札がつく移籍ビジネスの理にもかなっている。
先日、フランスのクレールフォンテーヌ国立フットボール学院を訪ねたら、入寮して間もない15歳未満の子どもたちがすでにクラブとの契約を済ませていた。鉄は熱いうちに打て。逸材を見つけたら猛スピードで出世の階段を上らせる。そんな大国の育成サイクルに追いつくためには、まずは私たち大人が固定観念を捨て、頭の回転を速くしなければ。
(国際サッカー連盟〈FIFA〉カウンシルメンバー)


国際サッカー連盟(FIFA)カウンシルメンバーの田嶋幸三さんが日本サッカーの「これまで」を振り返り、「これから」に思いをはせる寄稿コラムです。