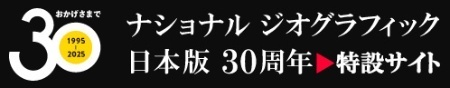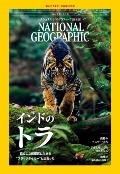大きな自然と小さな人間
荒々しい岩肌が露出し、大きな岩が転がる谷を、川は蛇行していく。水面すれすれに架けられた簡素な木の橋には、3人の姿がある。旅の途中だろうか。
写真には「ミサワ(日光の山あいの川)」と英語の説明が残る。日光市歴史民俗資料館に問い合わせると、この川は華厳滝に発し、鬼怒川に合流する大谷川だろうという。撮影場所は、紅葉の名所として有名な国道120号線の第一いろは坂の終点付近、深沢橋辺りのようだ。
明治中頃に出版された『日光案内』には、「四方の景色已(すで)に人間界に遠く全く深山の趣あり…… 右の方頭上にかかる大磐石(だいばんじゃく)は屏風を立てるが如く」とある。
男体山の火山活動で形成された大谷川流域では、もろくて崩れやすい地質と急峻(きゅうしゅん)な地形、雨の多い気候によって、土砂災害が頻繁に起きてきた。そのため大正時代以降、砂防事業が進められた。崩壊地の斜面を安定させて土砂生産を防ぐ「山腹工」、流出する土砂を調節するための「砂防堰堤(えんてい)」、川床や川岸が削られるのを防ぐ「床固工」や「護岸工」などだ。
第一いろは坂を下り切ると、道は大谷川と並行する。そこには、いくつもの砂防施設があり、川はかつてより人間界に近づいたように見える。――大塚 茂夫(ナショナル ジオグラフィック日本版)