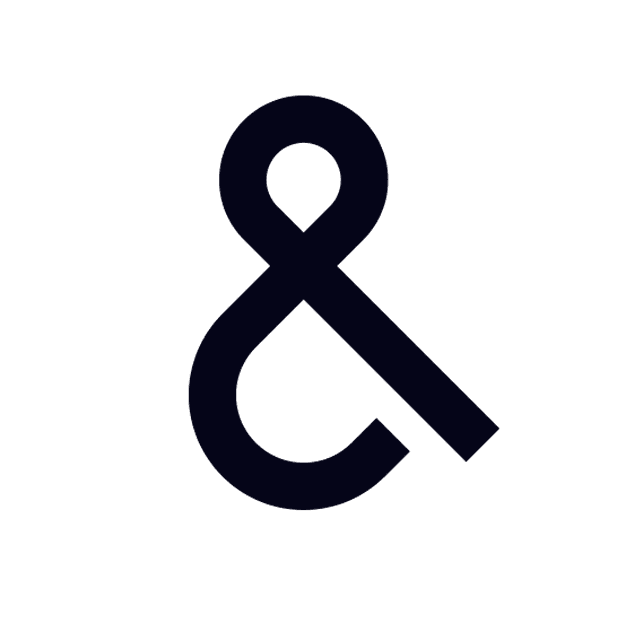秋風かおる10月のパリ、モンパルナスのにぎやかなランチタイム。レストランが軒を連ねる小道に、明るいピアノと歌声が響く。音のする先がまさに、目的地のレストラン「Sous les cerisiers(ス・レ・スリジエ)」。日本人シェフのさくらフランクさんが切り盛りする、和食ベースのフュージョン料理で評判のお店だ。
「絶対に来てほしい、日本酒の試飲会がある」。パリ在住日本人の食いしん坊つながりで、さくらさんから声をかけてもらって、足を運んだ。彼女の作る料理は絶品だが、今日はホスト役に徹して、山形県の日本酒と美味を伝えるイベントに場を提供するという。
「フランスには多くの酒蔵さんが進出しているけれど、山形県のお酒はまた、特別なの。酒造研究の神様みたいな小関敏彦先生のもとで、酵母の開発、山形産酒米の開発と、それを生かしたお酒造り。熱意あふれる山形県酒造組合の蔵元さんたちが集ってね……お酒はもちろん素晴らしいし、皆さんの雰囲気も最高だから!」
熱いお誘いに二つ返事で応えて参加したのが、山形県酒造組合がイタリアとフランスで開催する「GI山形・日本酒マスタークラス 酒と食のマリアージュ・ランチ」だ。組合の小関特別顧問と4人の蔵元、山形が誇る名イタリアン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行オーナーシェフが、パリの業界人30人のゲストに、山形が誇る12の美酒と8皿の美食を披露した。
豊かな水系がはぐくむ山形酒を講義
会はお誘いの言葉通りに楽しおいしく、ゲストもホストも頰を染めての大盛況。パリの日本酒をめぐるウェルカムな空気に満ちた、その模様をルポしよう。
開会前のピアノを奏でたのは、鯉川酒造11代目当主・佐藤一良社長。おもむろにピアノを離れると山形県組合の会長として挨拶し、サプライズで会場の空気を和ませる。パリで日本酒関連のイベントには少なからず参加した筆者だが、このように楽しい演出は初体験だ。
続いて小関顧問よりスライドを用いて、日本初、県単位のGI(地理的表示=Geographical Indication)認証を持つ山形酒と、それを生む自然、人を伝える講義が始まった。写真を豊富に用いて、雪の重要性を説明する。
寒気が浄化する大気、酒米の田植えを支える大量の雪解け水。そして酒造りには欠かせない、六つの山が恵むミネラル豊富な地下水。蔵王山系の硬水を始め、特徴豊かな山系の水質の解説には、プロのワイン醸造家も関心深そうに聞き入った。
ゲストが特に注意深く耳を傾けていたのは、山形県が41年前から継続して開発している酒米の品種についてだ。「日本酒のコメといえば山田錦」の知識はあるゲストたちにとって、精米歩合によって変わる日本酒の種類ごとに、最適の性質のコメ品種を選んで植える手法は新鮮に映ったようだ。
「製造法や、土地と水の特徴が味を作ることなど、日本酒とワインには響き合う点がありますね。日本酒はこれまでに味わったことがありましたが、こんなに種類があって、味わいの幅が広いのは、うれしい驚きでした」
ゲストの一人、フランス醸造学者協会会長のエマニュエル・フルトーさんは言う。
環境、材料の説明の次は、それを醸す人。山形県酒造組合の取り組みや、若手技術者が集う「山形県研醸会」の活動では、この場に来られなかった関係者の姿を伝えた。海外の輸出状況や欧州各国での山形酒の輸出量が好調に伸びている様に触れると、佐藤会長がおもむろに立ち上がった。
軽快な挨拶とともに流されるのは、山形県酒造組合のオリジナル・ソング。真面目な勉強モードが音楽と共に一気になごみ、純米大吟醸『山形讃香(やまがたさんが)6BY』で乾杯となった。前年の県内品評会で最上の評価を得た蔵元だけが醸造できる、特別な酒だ。
日本酒に合わせたフランス食材の8皿
ここからは、奥田シェフと4人の蔵元に会の進行をバトンタッチ。各々が「これぞ」と持参した酒をプレゼンし、その特徴と魅力を熱く語る。合わせる料理は、山形の酒を知り尽くした奥田シェフが、風味豊かなフランス食材との絶妙なマッチングで提案。メニューは事前に熟考されたが、シェフが現地で手に取った食材にインスパイアされ、即興で作られた皿もあった。
そのマッチングのさまは、写真を中心にご報告しよう。
1皿目は「小エビのベニエ」。合わせる東北銘醸の本醸造うすにごり「初孫は号」は、低温醸造した発泡酒。食事の始めと揚げ物にぴったりの華やかさで、ゲストを惹(ひ)きつけた。
2皿目は「キャビア海苔巻きとサーモンマリネ寿司」。まろやかで深い竹の露の純米吟醸「白露垂珠(はくろすいしゅ) 美山錦55」が、キャビア独特の潮味とサーモンの脂味とハーモニーを奏で、舌を楽しませる。
3皿目「笹かまのプランチャ焼き マリニエール・ソース」では、これが笹かま?と一瞬驚く食感に。ソースのきのこ風味が、心地よい渋みを持つ純米大吟醸「白露垂珠 改良信交」と響き合う。
4皿目の「じゃがいものドフィノアとフォアグラポワレ」。食べ応えのある皿は、個性の異なる二つの酒で食べ比べる。1本目は初孫の純米大吟醸「ふなまえ直詰 PLUS」、フルーティで濃厚、かつキレのいい後味がフォアグラとマッチ。
4皿目の2本目は加茂川の純米大吟醸「KAMOGAWA KIMOTO CLASSIC」。純米大吟醸とは思えない酸味のインパクトとコクのある飲み口。稲作と同じ水で仕込む独特の風味には、ゲストからも驚きと称賛の声が上がった。
5皿目の「アサリとキノコの酒蒸し」には、燗酒(かんざけ)に定評のある鯉川酒造の純米吟醸「あたためますよ」を合わせた。調味料を効かせた酒蒸しの味わいを、まろやかな燗酒が包むようにまとめ、喉奥に届ける。
6皿目の「アンディーブのブレゼ、ブールブランソース」には、清明できれいな飲み口の竹の露「白露垂珠 純米大吟醸 BUONO!(ボーノ!)」。欧州向けのテーブルワインをイメージした酒蔵の意図を知る奥田シェフ、通常白ワインの酸味を効かせるブールブランソースにこの酒を使い、すっきりとキレのいい後味の、新感覚のソースに仕上げた。
7皿目は肉のメイン料理「鴨ローストバルサミコ、アスパラガスのベアルネーズソース焼き」。力強い肉とソースの味にマッチしうる、うまみ自慢の生酛(きもと)造り、しかも個性の全く異なる2酒を揃えた。東北銘醸の本醸造「初孫 伝承生酛」はコハク酸の効いた濃醇(のうじゅん)な味わい。加茂川からは10年熟成の生酛純米古酒から醸す貴醸酒「加茂川 2018」を、その優美な化粧箱とともにプレゼンテーションした。
テイスティングのラストを飾るデザートは「焼かないクレーム・ブリュレ」。甘みのほとんどない鯉川酒造の辛口特別純米酒「ブラック鯉川」を敢えて合わせ、大人ならではのデザート賞味体験を演出した。
料理の合間に客席に出て、ゲストと談笑する奥田シェフ。「今日はフランスの方に『こんな手もあるよ』と伝えたい思いがありました。日本酒とバターを合わせてソースにしたり、酒蒸しで貝の味わいの深みを引き出したり。日本酒が食材の旨みを引き立てることを、フランス料理で見せました」
パリの人々が求める新しい日本酒
めくるめく、という言葉がふさわしい、銘醸酒の数々。杯を瓶を重ねるうちに会場の雰囲気も温まり、ゲストとホストの会話は、言語の壁を超えて盛り上がる。佐藤一良社長のピアノ演奏と熱唱で終幕を迎えた後も、ゲストたちは名残惜しそうに、未知の美酒とその作り手との出会いを満喫していた。
パリ中心部の高級寿司店「Sushi B Paris(スシ・ベー・パリ)」のソムリエ、ホン氏は四皿目とテイスティングした「KAMOGAWA KIMOTO CLASSIC」が特に印象に残った、と語る。
「香りと酸味のバランスが独特で、ウィスキーのように食後酒でもいけるお酒。日本酒を飲み慣れてきたパリジャンは今、さらに発見を求めています。そんな顧客に新しい経験を提供できる一本だと感じました」
「日本酒の試飲会がここまで盛り上がるのは、本当に珍しいです。私が知る範囲では、初めてかも」
「茶懐石 秋吉」の女将(おかみ)・秋吉三鈴さんは、立ち去り際に賞賛の言葉を残した。本場の京都の茶懐石を提供し、ミシュラン一つ星を得た、パリ日本食シーンのキーパーソンだ。
「小関先生がロジカルに酒造りを話した後、酒蔵さんが全員で楽しませて盛り上げる。論理と感情が合わさって、心に響く会になったと思います」
これまでに海外での試飲会を経験している酒蔵の人々も、今回のイベントでは大いに手応えを感じたという。多彩な日本酒文化を受け入れる準備が整ったパリ、その可能性を証明した山形人たちの言葉は、海外市場を狙う日本のものづくりにとって、大きなヒントになるだろう。
「ゲストが皆さん、本音で『いい』と言ってくれているのを感じました。私は『山形は日本酒のシャブリを目指す』と言い続けてきましたが、今日の反応で、それを再確認できました。山形の酒蔵は皆、今日のレベルのプレゼンができるので、ぜひ今後も続けていきたいです」 (山形県酒造組合会長・鯉川酒造 佐藤氏)
「人と人が顔を合わせて、一緒にテーブルを囲むからこそ、伝わる本音を感じられました。そこで高く評価していただけて、大きな自信になりました」( 加茂川 小島氏)
「このような試飲会は、盛り上がってナンボ。楽しい雰囲気の中でペアリングを味わっていただけてうれしいです。海外は日本酒ビジネスで今、唯一伸びている市場。これから海外で認知されていくには『甘くてスッキリ、キレイ』なだけではなく、いかに個性的な日本酒を作っていけるかが、違いになってくるでしょう」(東北銘醸 佐藤氏)
「過去最高の素晴らしい機会になりました。食と酒、両方の力が10ずつかけ合わさって、100倍の効果が出たと思います。ゲストと共有性が見つかってうれしかったです」(竹の露 相沢氏)
「パリの試飲会はこれが3回目ですが、ゲストの理解度がどんどん深まっていますね。これは継続して取り組んできた効果です。私たちが売っているのは、モノとしての日本酒だけではなく、そのカルチャー。文化を売るというのは、ファンを増やすということ。そのためには時間をかけて、コミュニケーションを重ねる必要があるのです」(山形県酒造組合特別顧問 小関氏)