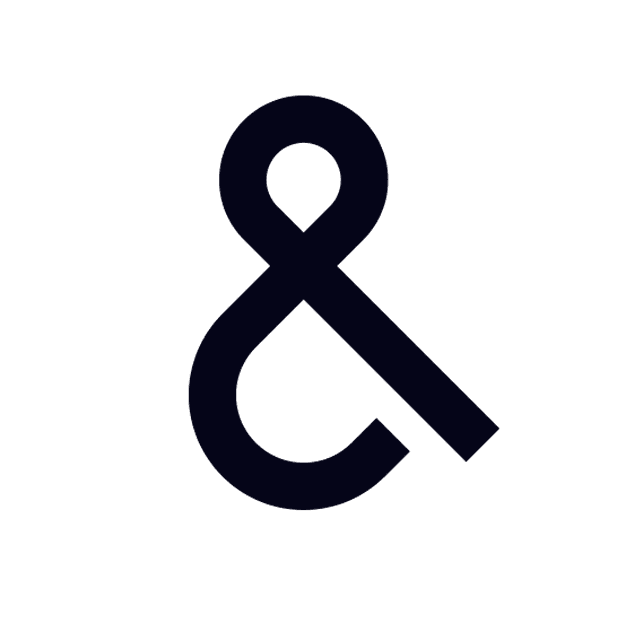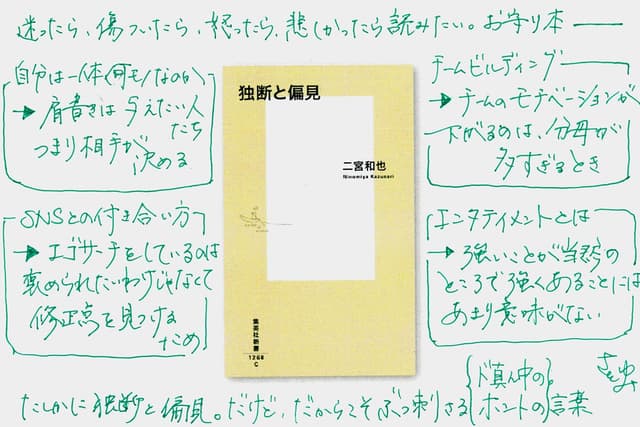江戸時代中期に開窯(かいよう)し、関東において特に古い歴史を持つといわれる茨城県の笠間焼。土や焼き方などに縛られぬ自由度の高さが特徴で、多くの個性的な作家を輩出しています。パステルカラーで優しい風合いの食器類が人気の町田幸さんもそのひとり。笠間焼の魅力や、作品に込める思いを伺いました。
何にでもなれる自由さ、笠間焼の個性
——町田さんが陶芸家として活動している「笠間焼」の特徴を教えていただけますか?
江戸時代に窯が開かれた当時は、周辺で採れた赤土を使って甕(かめ)や鉢といった日用品などを作っていたそうです。そのころの面影は、水戸の偕楽園で梅酒などを入れる土産用の瓶などに見ることができるでしょう。ただ、そうしたタイプの笠間焼は時代とともに衰退してしまいました。1950年代に入ると、再び笠間焼を盛り上げようという機運が高まり、現在の茨城県立笠間陶芸大学校の前身である「窯業指導所」が作られ、のちに、陶芸団地や窯業団地も築かれたことで、全国から作家が集まってくるようになりました。
個人の作家が活躍するという点では、一種の民芸村に近いのかなと。いろんなルーツを持つ作家が集まっているため、備前焼なら薪で焼いた土の風合いというような、これといった共通点がほぼありません。逆に言えば、何にでもなれる自由さが笠間焼の個性であり、魅力と言えるでしょう。
きっかけは、縄文土器
——町田さんご自身は、どのような経緯で笠間焼の道に進まれたのですか?
笠間と同じ茨城県の日立市出身なので、子どものころから知ってはいましたが、焼き物の道に進むつもりはなく、大学では日本考古学を専攻したんです。映画『インディ・ジョーンズ』みたいな世界に憧れていました。
でも、いざ学術研究の世界となると調査報告書を読み込み比較検討し、論文を執筆することが中心になります。じっと座ってデスクワークをするより、手足を動かす方が性に合っていると感じていたとき、「実習で縄文土器を焼いたことが楽しかったな」と記憶がよみがえりました。それで、卒業後は焼き物をやりたいと思ったんです。
——陶芸作家の入り口が、まさか考古学だったとは驚きです。
(笑)。ただ、うまくはいきませんでした。就職活動中の2002年は、就職氷河期まっただなかで、窯業指導所に相談に行ったものの「焼き物で食べていくのはかなり難しい」と言われました。そこで、陶芸の道をあきらめ就職することにしたのですが、就職先は何かを作る会社がいいと思い仏壇メーカーに入りました。デンマークやフランスの工房に仏壇のデザインを発注したり、ベネチアングラスの仏具を合わせたりと、ユニークなものづくりをしていましたね。
けれど、メーカーといってもあくまで発注する立場。お客様に自社の製品を説明するとき、自分が制作にかかわっていないため自信をもって伝えられないもどかしさを感じるようになりました。そのとき、「私は、大きな仕事の一部分を担うより、最初から最後までを自分で把握し、責任を持って完結させたいタイプなんだ」と気づいたんです。その点、焼き物は土をこねるところから窯で焼き、お客様に届けるまで全工程を自分で担うことができます。やっぱり私は焼き物がやりたいんだという気持ちが再燃したんです。
——原点に立ち返ったのですね。
ええ。大学時代に惹(ひ)かれた縄文土器は、1万年以上も前に生まれ、手近にあった土をこね、野焼きされたものです。そうした手ごたえのあるものづくりがしたいと思いました。
実は、その仏壇メーカーの同僚の一人が、笠間焼の窯元の妹さんで、その方の応援も力になりました。自分の思いを打ち明けると、「どこかに弟子入りするなら、自分が好きな作家のところがいい。年に1度の笠間焼最大のお祭りである陶炎祭(ひまつり)は笠間焼の作家がみんな参加するから、まずは自分が好きな作家を見つけてみては」と、助言してくれたんです。お祭りではマップを片手に、気になる作家さんをチェックして歩き回りました。後日、その時に作品を見たおひとりで、国際陶芸展で金賞などを受賞している小林政美先生に師事することになったんです。
自分にないものへの憧れ
——修業は厳しいものでしたか?
弟子入りや修業と聞くと、大変そうだと思われるでしょうが、実際は穏やかなものでした。師匠は食器などの日用品というよりは、オブジェなどを得意とする作家で、とても自由な気風の方だったんです。師匠が来る時間に合わせて、コーヒーをセットするのが日課でした。師匠の制作のお手伝いをする以外の時間は、好きに使っていいと言ってくださっていたので、基本練習に多くの時間を費やせたんです。
ただ、私は芸術大学などで陶芸を学んだわけではないので、師匠の様子を見よう見まねで学びました。師匠がろくろを回すときは私も格好だけはまねてみたり、手びねりを教えていただいたりして、少しずつ技術を習得していきました。師匠のところでは、ろくろでの制作を志す人は、急須を習得したら独立に向けて動きはじめる時期がきたことを意味します。約1年半たったころに師匠から「そろそろ急須を作りましょう」と言われたときは感慨深かったですね。卒業後は、師匠の門下生が皆通ったように、窯業指導所の釉薬(ゆうやく)科に進み半年間専門的な学びを深めてから独立しました。
——師匠の小林さんは、まさに笠間焼の自由さを体現している作家のようです。
おっしゃる通りです。お人柄からも分かるように、師匠の独創的な作品に強く惹かれて弟子入りしたのです。でも、いざ自分で自由な作品を作ろうとすると、「はて、どうしよう」と手が止まってしまったんです(笑)。そのときに、自分にないものだからこそ憧れたのだと気づいたんです。師匠の作品を鑑(かがみ)とし、自分のやりたい方向性を知れたのも弟子入りしたお陰だなと思っています。