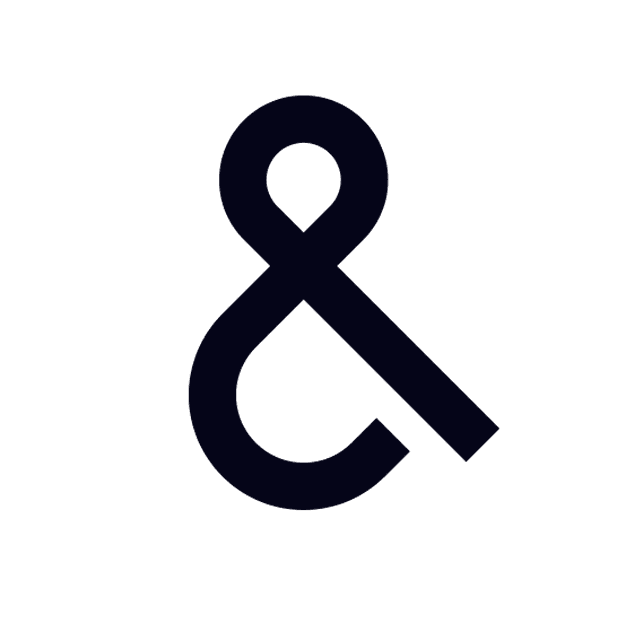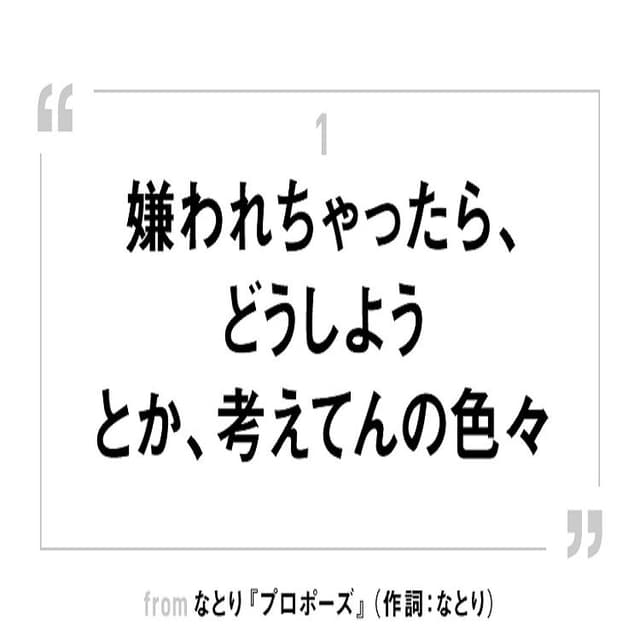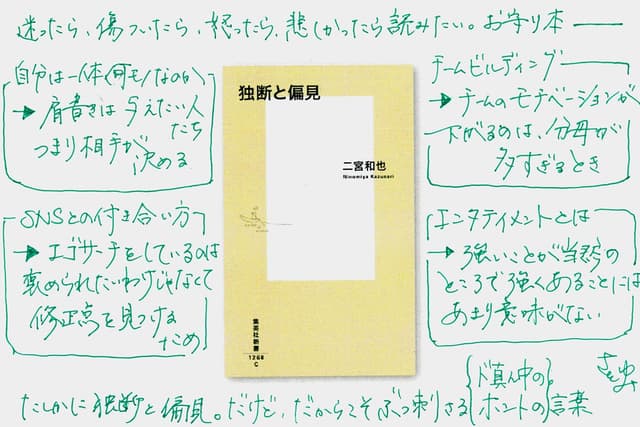2019年に日野市の生産緑地を借り受け、たった一人で農園「ネイバーズファーム」を立ち上げた梅村桂さん。東京大学農学部に進学し、いずれは国際貢献する仕事に就きたいと考えていた梅村さんが、なぜ地元・東京で農業を始めたのでしょうか。梅村さんが思う、農業の魅力や可能性について伺いました。
生産者のこだわりをトマトで
――はじめに、「ネイバーズファーム」について教えていただけますか?
私が代表を務める「ネイバーズファーム」は、2019年に東京・日野市の土地を借り受け、新規就農したもので、法人化したのは3年ほど前です。最初は今の半分ほどの農地を私一人で耕し、トマトなどを栽培していました。栽培から出荷のための袋詰め、販路開拓など全部やらなきゃいけなかったので無我夢中でしたね。
2年目に設備投資してハウスも建て、最初の従業員が来てくれたのもその年でした。今は社員が2名、パートさんが2名、地域のボランティア数名がお手伝いに来てくださり、この場所以外の土地も借りて生産量も増えました。日野市はボランティア育成などに力を入れており、農業の講座を受けた方が市を通して農家に派遣される仕組みがあるんです。皆さん楽しく自主的に取り組んでくださっているので、とてもありがたいです。
ハウスの水耕栽培は、畑仕事でも土を使わないため服もあまり汚れず、仕事帰りにそのまま友達と食事に行けますし、長期休暇も可能なんですよ。
――従来の農業のイメージと異なり、働きやすい環境なんですね。「ネイバーズファーム」では、トマトを主軸に作っているのですね。
はい。ぶっちゃけ、トマトしかやったことなかったので他の野菜は作れないだろうなと思ったんです。ただ、実際に育ててみると野菜の中でも栽培が難しいことがわかってきました。コントロールする項目が多いので、その分天気任せにできないんです。でも、逆に言えば、自分次第でうまく制御できる。販売するとき、生産者のこだわりを出せる野菜じゃないと直売所などで手に取ってもらいにくいので、トマトは「ネイバーズファーム」にぴったりなんです。
――生産者のこだわりとは?
よくトマトって「水を絞ると甘くなる」みたいに言われますよね。甘くてすごく濃縮されたトマトにするか、みずみずしくてフレッシュなトマトにするかは、水や温度管理など環境を制御することである程度狙って作れるんです。「ネイバーズファーム」では、ハウスでの水耕栽培で、水の量や太陽光の制御なども自動化しています。トマトは、土で育てると連作障害が起きやすいため、続けて同じ場所で作るためには土壌に強い薬を使うこともあるんですが、水耕栽培はそうした心配もありません。また、害虫も少ないため農薬も減らせ、都のエコ農産物の認証をいただいています。
――これまでに、ご苦労されたことは?
最初は販路が定まっていなかったので、大量にトマトが採れてしまい途方にくれました。大量のトマトを前に、今日、販売先が見つからないと廃棄することになる!……そんな日々が続いて。スタッフに大量に持ち帰ってもらったり、いろんな人に流通業者さんを紹介してもらったり、ECサイトを立ち上げたり……思いつくことは全部やりました。
また、当初は水の管理を試行錯誤していたので、実が割れやすく流通で扱いにくかったため、取引してもらえないのも悩みでした。でも、質のいいものを安定して出荷できるようになると、いろんなところから声がかかるようになって。しかも最近は、野菜の高値が続いたり、地元産の野菜が求められているので、常に需要のほうが多い状況ですね。
東京で、食べる人の顔が見える農業を
――そもそも、東京で新規就農できるとは意外でした。
私もたまたまテレビか何かで目にして、「東京で農業できるんだ」って驚いて。そこから、情報収集を始めたんですが、知っていくと都市部の農地には歴史がある一方、高齢化や跡継ぎ問題などを抱えているという実情も見えてきました。農地の情報も思うように集まりませんでした。
実際、借りられる農地はとても少ないんです。それぞれの地主さんには色んな考えがあり、「トマトを作る」こと1つとっても、考えが合うかどうかはわかりません。それが許可されても、ハウスを建てることに理解を示してくださるかはまた別です。さらに相続などの問題も絡むので、長期で土地を貸してくださる方は限られます。また、都市計画などの話も関係するため、複雑で難しいんですよ。結局この土地に出会うまで、約2年かかりました。
――途中で心が折れなかったのはなぜでしょう。
そもそも、都市農地での就農はハードルがありましたが、近いうちに新しい法律ができるだろうと審議がされ始めていたタイミングだったんです。法律ができ地主さんにもその情報が広まれば、「土地を貸してもいいな」と思う人が出てくるんじゃないかと考えました。同時に、都市の農地も注目され始めていたので「待ってれば、きっと潮目は来るな」と。とはいえ、都市部の土地は資産価値がめちゃめちゃ高いので、「マンションにしちゃった方がいいな」と思う方がまだまだ多いとは思うんですけどね。
――東京大学在学中から、就農しようと?
それが全然(笑)。在学中は、国際開発の分野に興味があり海外で働きたいと思っていました。実際、フィリピンやタンザニア、スリランカなどに行き、そこで農業に興味を持ち始めたんです。いずれはJICA(国際協力機構)などで働き、農業専門の技術職として開発の分野に携わるなど、都市計画や社会基盤を専門にして海外で活動したいなと思っていました。
――卒業後は、大規模農園の立ち上げに携わったとか。
新卒で就職した会社で、福井県で大きなトマト農場を立ち上げるプロジェクトの担当になったんです。事前に1年間農家に入って栽培のイロハから教えていただいたのをはじめ、生産ラインの組み立てや人への対応、販売や営業、流通などを身につけました。ハードモードな日々でしたが、自分なりに全体像が見えたのは大きな収穫でしたし、自分の裁量で育てるなかで「こういう管理をすれば、植物がこういう姿になるのか」みたいなことが目に見えてわかると、いいものを作ることへの終わりのない探求みたいな面白さを感じるようになったんです。
一方で、地方で大きな農場を造り、大量に野菜を作り、大量に都市部に送るやり方が、自分が思い描いていた農業とはちょっと違うなとも思ったんです。それで、身に着けたスキルを活かし、自分が生まれた東京で、食べる人の顔が見える農業をやれたらいいなと思うようになり、3年勤めた会社を辞めました。清瀬市にある個人の農家さんで数年修行を積んだのち、「ネイバーズファーム」を起こしました。
――国際支援を視野に入れていた梅村さんが、今は地域密着で就農しているとは不思議です。
確かにそうですね(笑)。国際開発農学を選んだとはいっても、国際協力への道が開けるというよりは、日本のローカルな農家さんのところに行き、フィールドワークでいろんな調査をするみたいなことをやっていました。また、農業系の会社でインターンを始めて、全国の農家さんにインタビューしてフリーペーパーを作っていたんです。いろんな方にお話を伺ううち、「なんか、農業って普通に面白いじゃん」って思うようになっていたんですよね。
それと、自立して生きられるようになりたいという気持ちも強くあり、そのためのスキルを手に入れたいとも思っていました。学業の間にいろいろと見たり経験したりする中で、一生飽きなさそうで、一生必要そうなことはないだろうかと、常に意識していましたね。