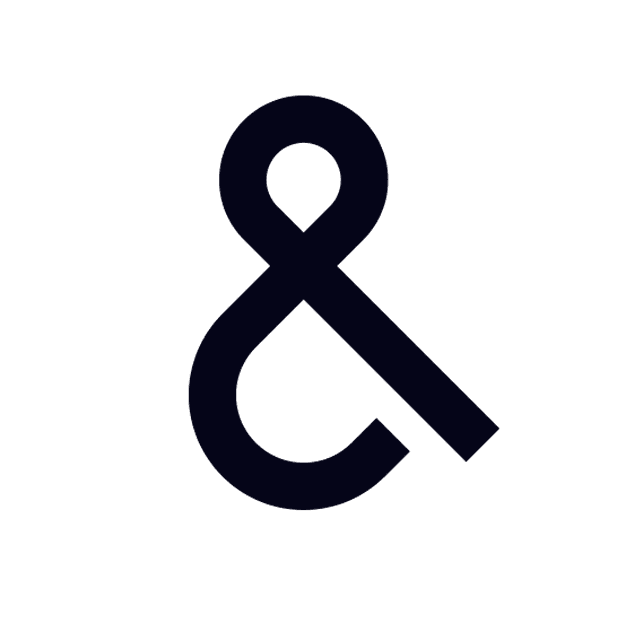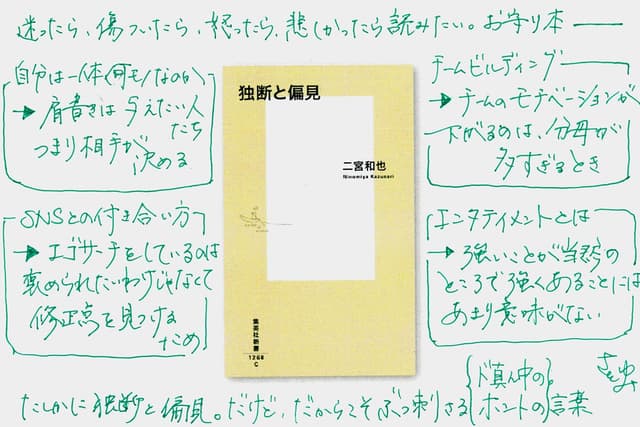社会で「妊活」を支える機運が少しずつ高まっているなか、身近な自治体でも不妊治療にかかる費用の助成や当事者の相談事業などの支援態勢を整えつつあります。公的な妊活サポートはいまどうなっているのでしょうか。
不妊治療も保険適用に。「+α」の部分を支える自治体の助成
2022年4月から、人工授精などの一般的な不妊治療、体外受精、顕微授精といった不妊治療が国の公的医療保険(健康保険)の適用対象となり、窓口での自己負担は3割となりました。人工授精ならそれまで1回2〜3万円だったものが、5千円程度で済むようになったのです。
妊活を支援するNPO法人Fineの野曽原誉枝理事長は、それでも治療によっては依然として負担が大きいと言います。体外受精の場合、1回あたりでかかる費用は平均で約50万円と言われていますので、3割負担でも15万円になります。
「保険のおかげで体外受精や顕微授精にチャレンジしやすい環境になりましたが、何度も治療を繰り返すケースもあり、費用が高額となって諦めてしまう場合もあります。その意味で自治体の助成は大きいのです」
例えば青森県ではこの自己負担額の全額を負担、富山県では保険適用外となる7回目以降の治療に対して一回につき上限30万円まで助成しています。
さらに、保険適用されていない治療や薬に対して助成する自治体もあります。
その一つが東京都です。都は特定不妊治療費(先進医療)助成制度として、保険適用された治療と同時に行う先進医療の自己負担分に対し、一回につき15万円を上限として助成を行っています。都によると、2023年度に12520件の助成が承認されました。
Fineが2022年に行った自治体アンケートによると、独自の経済的助成制度を設けていると回答したのは20府県で、全都道府県の43%だったそうです。(『NPO 法人 Fine「不妊・不育症患者への自治体独自の支援体制アンケート調査」』)
Fineのアンケートによると、経済的助成以外の支援として同様に「当事者の精神ケア」を行っている、もしくは予定しているという自治体は全都道府県の53%でした。
Fineも自治体の委託を受け、不妊の体験のあるカウンセラーが対面やZoomで相談を受けています。また、長崎県や神奈川県横須賀市など、LINEを活用した24時間対応の民間の妊活相談サービスを導入している自治体もあります。
仕事との両立を後押し 企業に奨励金も
都では当事者だけではなく、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を支援しています。それが2018年度から2024年度までの「働く人のチャイルドプランサポート事業」です。
事業が始まったのは都民提案がきっかけだったそうです。女性が不妊治療をしながら仕事を続けるのはハードルが高いという悩みに応えるための制度で、仕事と不妊治療の両立に積極的な企業に対して奨励金40万円を支給、また企業向けに研修を実施しています。
奨励金を受け取るためには、会社の管理職全員が都が実施する研修に参加すること、社内の相談体制を整えること、不妊治療のための休暇・休業制度を就業規則に定めることなどが求められています。
2018年から2023年度までに、奨励金を受け取った企業は1006社に上ります。事業は2025年度から「キャリアとチャイルドプラン両立支援事業」として、卵子凍結に関わる研修や制度整備にも拡大されました。
事業を担当する都の産業労働局・雇用就業部は、このような施策は「誰もが働き続けられる、持続可能な社会の実現のため」と言います。不妊治療だけでなく、育児や病気など様々な事情があっても働き続けられるためには、職場の理解と環境整備が欠かせないからです。
注目される「プレコンセプションケア」への取り組み
このように、自治体は助成金や啓発、企業への理解促進などの施策をしていますが、「どれも重要な施策ですが、もっと早期の支援も欠かせない」と話すのは、不妊治療と仕事の両立を支援するNPO法人「フォレシア」の代表理事、佐藤高輝さんです。
日本で不妊治療を始める人の多くが30代後半と言います。結婚してそろそろ子どもをと思ったときに不妊が分かり、そこから治療を始めるというのが一般的なためです。
しかし、年齢が高いほど赤ちゃんを授かるのは難しく、日本の体外受精の成功率は諸外国に比べても低いといわれています。そこでここ数年、取り組む自治体が増えているのが、より若い頃から将来の妊娠に備える「プレコンセプションケア」です。
東京都は2020年に架空の「妊活課」というポータルサイトをオープンし、当事者や周りの人が情報を得やすいようにしています。ここではイラストがふんだんにつかわれていて、妊娠の仕組みや不妊についての基礎知識をクイズ形式で解説しています。知識の普及・啓発に力を入れるのは、「これから子どもを持ちたい人に、早いうちから知ってもらうのが重要」(都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課)との考えからだそうです。
プレコンセプションケアでは、正しい知識を持つことからさらに一歩踏み込み、女性なら血液検査や婦人科の検査で妊娠のしやすさ、男性ならホルモンや精液などを調べるなども含まれます。
東京都では講座を受けた18歳から39歳までの男女の希望者にプレコンセプションケアの検査費用を助成しているほか、福岡市では30歳になる女性に、卵巣の機能や卵子の数を調べる検査を500円の自己負担で受けられるクーポンを配布しています。
自治体のこのような動きについて佐藤さんは「不妊治療助成は少子化対策の一環として重要ですが、晩婚化などの社会的背景もあり、期待される成果に直結しにくい側面がある。プレコンセプションケアは、より早期の支援として、そうした背景にもアプローチできる根本的な対策になり得る」として、今後も増えていくだろうと予想しています。