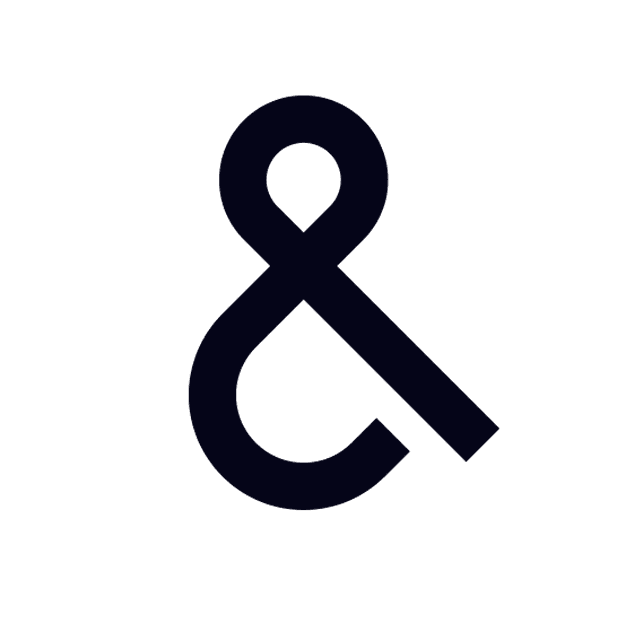古川・国府盆地と五つの城 姉小路氏城館跡の全体像
JR富山駅から特急ひだに乗り、飛驒(ひだ)古川駅を目指す。宮川沿いに山間を縫うように南下すると、南北に細長い古川・国府盆地に抜ける。そのほぼ中央にあるのが、飛驒古川駅だ。富山県と県境を成す岐阜県北部の飛驒地域は約92%を森林が占め、居住できる平地は二つの盆地(高山盆地、古川・国府盆地)や河川沿いの段丘地などに限られる。
古川盆地は古代から飛驒の中心地のひとつだったと考えられ、中世にはたくさんの城が築かれた。その多くは、古川盆地への侵入を阻止するかのように盆地を囲む山の端や街道沿いに分布している。ひしめく城のうち、この地域を支配した姉小路(あねがこうじ)氏の歴史を物語る5城(古川城跡・小島城跡・野口城跡・向小島〈むかいこじま〉城跡・小鷹利〈こたかり〉城跡)が「姉小路氏城館跡」として2024(令和6)年2月に国史跡に指定されている。
姉小路・三木・金森 三つの時代で読む地域支配の変遷
たまらなくおもしろいのは、古川盆地を舞台にした15〜17世紀初頭の動乱や地域支配の変化が五つの城を通してリアルに感じられることだ。これまで山城に埋もれていた地域の営みが、発掘調査や文献調査などの総合的な学術調査・研究で掘り起こされ、壮大な歴史ストーリーの輪郭が浮かび上がっている。
現地を訪れてこそ、その醍醐(だいご)味がよくわかる。『長篠合戦図屏風(びょうぶ)』や『関ヶ原合戦図』などの大きな屏風絵を目の前にしたときのような、奮い立つスペクタクルでもあるからだ。大きな屏風絵を前にすると、まるで自分が高台から実際に戦場を見渡しているような気分になるだろう。同じように、古川城や小島城に登って古川盆地を見下ろすと、かつての動乱が目の前で起こっているような感覚になるのだ。
古川盆地という山に囲まれた空間の中で、どのように人々が生き、時代とともに城がどう変化していったのか、五つの城を通して想像できる。
姉小路氏城跡の歴史は、大きく三つの時代に分かれる。①姉小路氏時代(15世紀末から16世紀半ば)、②三木(みつき)氏時代(16世紀半ばから16世紀末)、③金森長近時代(16世紀末から17世紀初頭)だ。五つの城は築かれた目的や改修された時期・理由が異なるため、まずは大まかに歴史を整理しておくといいだろう。
五つの城がこの三時期においてどのような位置付けにあったのか、三時期にどのような影響を受けてどう変わっていったのかに着目すると、それぞれの城の足跡がよくわかるはずだ。