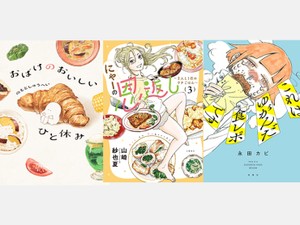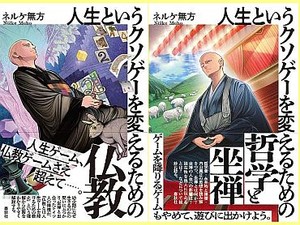綿矢・金原ショックで就職に逃げる
2016年に角川短歌賞、22年に第1歌集『輪をつくる』で現代短歌新人賞。同年、現代詩手帖賞、第1詩集『冬が終わるとき』で中原中也賞最終候補。そして2024年、『ダンス』で新潮新人賞を受賞し、同作が芥川賞候補に――。
あまりにも華麗な受賞歴に、この連載に出てもらうべきか迷った。天才の話は凡人の参考にならない。ところが、本人はずっと劣等感を抱えていたという。
「最初の挫折は小学5年生の時。漫画家を目指していた私は少女漫画誌『りぼん』の通信講座を受けていました。福岡で出張マンガ教室が開催されるというので、友達と2人で応募したら友達だけが受かったんです。その子はとくに漫画家を目指しているわけでもなく、通信講座も受けてなかったのに。ショックで漫画を描くのをやめました」
高校生になると、小説家を目指すように。実作指導がある早稲田大学と日本大学の文学部に進路を絞り、早稲田に合格した。いよいよ文筆の道へ――。
「ところが、一瞬で挫折したんです。山口の田舎から出てきた私は、都会の同級生たちとは読んできたもの、見てきたものがまるで違う。同じクラスに『期待の新人』と言われるようなすごい才能の子もいて自信喪失。小説が書けなくなりました。親に無理させて東京に出してもらったのに、このまま4年過ごすわけにはいかないと、2年生からは就職に役立ちそうな社会学専修を選びました。でもそれも思い切れなくて、夜間の映画学校に入り、ダブルスクールしていました」
なぜ映画学校に?
「早稲田の先生に『どうしても書けないんです』って相談したら、『書けないなら書けないままでいたほうがいい』と言われて。他人の型を覚えて無理に100枚書けるようになっても、そのあと自分の作風を見つけられなくなるから、と。じゃあ書けない間は映画をやろうと思いました。私はストーリーを書くのが苦手。映画ならシーンとシーンのつなぎ合わせだからいけるかもしれないと考えたんです。一応、監督した作品がDVD化されたりもしましたが、経済的に夢を追う選択肢はなかったので、卒業後はふつうに就職しました」
でも、撮った作品がDVDになるってすごいこと。自分に才能があると思わなかったんですか。
「私、82年生まれなんですけど、ひとつ下の学年に綿矢りささんと金原ひとみさんがいて。綿矢さんなんか大学も同じ。自分とそう変わらない歳の人がすでにプロとしてやっていて、自分はヒエラルキーの底だという意識がずっとありました」
「思ってたんとちがう」新人賞
「結局、定時上がりの仕事に就いて空いた時間に小説を書こうと福岡で公務員になりました。けれどいざ公務員になったらめちゃくちゃ忙しいんですよ。毎日深夜残業で小説を書く時間なんてない。そこで始めたのが短歌です。短歌なら通勤時間で作れるし、ネットに投稿すればすぐ反応が返ってくる。それから、奇跡的に同期で小説家を目指している子がいて、その子と2人でフリーペーパーを作って喫茶店に置くことで創作欲をなだめていました」
転機は30代に入ったころ、ネットで見つけた短歌サークルに入ったこと。
「はじめて同年代で短歌をやっている人たちに出会い、短歌の雑誌や新人賞について教えてもらいました。30代になると、結婚するかしないか、この仕事を続けるか転職するか、いろんな選択が迫ってきて。自分が何をして生きていきたいのか考えたときに、やっぱりものを書いて生きていきたい、と。大学時代、努力しないまま諦めてしまった後悔がずっとあったんです。プロになりたい、というより、今度こそ努力し尽くしたい、という思いでフリーペーパーをやめ、短歌に専念して、賞に応募するようになりました」
応募しはじめて、わずか半年で角川短歌賞を受賞。
「これで歌人デビューだ、人生が変わるんだ、と思っていたのですが、実際は……。新人賞をとることへの期待値が高すぎたんです。受賞しても短歌の仕事は全然来なくて、でも競争の目にはさらされ、いろんな会や集まりに出なくちゃいけない。これまでの蓄積がないので自分の持ち味を掴めず、第一歌集が出るまで6年もかかってしまいました」
行き詰まった竹中さんは、小説や詩を書いては応募するようになった。
「短歌はもう応募できないので、他ジャンルに挑戦するしかなかったんです」
2022年、現代詩手帖賞を受賞。さらにようやく完成した第一歌集で現代短歌新人賞を受賞。
鍛錬するほど落選する袋小路
それでも小説への応募はやめなかった。
「土日は短歌や詩を作るのに使うので、小説は会社の昼休みの30分で3枚書くと決めていました。そうすれば1か月で100枚くらいになって応募できるんです。5大文芸誌を中心に、1年で6本くらい出していました」
あわせて自分で編み出した基礎練A、基礎練Bも取り組んだ。
「基礎練Aは、まず『坊ちゃん』や『こころ』といった有名な作品の構成をスケッチブックに書き出します。テーマがこうで、それに対してこういうキャラクターがいて、こんなイベントが起きて……って。で、その図式に自分の書きたいテーマをあてはめたらどうなるかを考える練習です。
基礎練Bは映画の10分のシーンを1時間かけてノベライズする、というもの。2週間続けるとだいたい映画1本分の小説になります。セリフや物語の展開といった、自分が苦手なところを中心に取り組んでいました。あとは『小説家になるために』みたいな指南書も読んだし、名作の書写もしました」
自分の30代を肯定していることに気がついて
が、努力すればするほど公募の結果は下がっていった。大学の先生が言ったように、型を意識しすぎるとよくないのだろうか……。
「応募者30人ほどのちいさな賞で14歳の子に負けたときには泣き崩れました。文学の教養も人生経験もさすがにこっちのほうがあるはず。こんなに努力しているのに、って。その次に書いたのが『ダンス』です。フリーペーパーを一緒に作っていた友人に『あなたの30代はどうだった?』と聞かれて『普通の人が高校生ぐらいで経験することを味わわせてもらった』と答えたことから着想しました。私は中学も高校も不登校まっしぐらで修学旅行に一度も行ったことがありません。そんな自分が、友人とフリーペーパーを作ったり、短歌の仲間と短歌合宿に行ったり、自分が思うより自分を楽しめていたことに気がついて」
なぜ『ダンス』は受賞できたと思いますか。
「ふたつポイントがあって、ひとつは私にこだわりがなかったこと。その頃、小説講座に通っていて課題のために適当に30枚くらい書いて出したのが『ダンス』の原型。自分との距離が取れていたのかもしれません。もうひとつは、それを読んだ先生が熱心に指導してくださったこと。もうちょっと派手なシーンを作った方がいいよとか、何度もアドバイスをしてくださいました。さっきの型の話と矛盾するようですけど、やっぱり新人賞には新人賞をとるためのメソッドがある。個性とメソッド、そのバランスが『ダンス』はちょうどよかったのかもしれません」
短歌で培った技術も盛り込んだそうですね。
「小説講座でよく受けた注意が、『面白いシーンは並んでいるけど何を読ませたいのかよくわからない』ということ。それは短歌の人が小説を書くときによく言われることみたいです。短歌はシーンだけでも成立しますからね。では、シーンの積み重ねとストーリーの何が違うかというと、ストーリーは主人公がなにか望みを持っているんです。両思いになりたいとか、変わりたい、とか。けれど私はそれがめちゃくちゃ苦手。主人公に何かを願わせないままストーリーを成立させるために見つけた方法が、時間を飛ばすことでした。どの場面を書いて、どこを書かないか。これに、短歌で身に着けた省略の技術が役立ちました」
短歌・詩・小説を同じ熱量で
最終選考に残ったという連絡を受けたときはどんな気持ちでしたか。
「会社の飲み会に行かずにひとりカラオケをした帰り道でした。思えばそれが最後の夢見心地の瞬間でした」
最後の……?
「受賞した瞬間から、小説も短歌と詩と同じで、ある意味〈タスク〉になってしまったんです。芥川賞候補になったときも、次この仕事ね、と言われたような気持ちでした。もちろん、喜びもあるのですが」
芥川賞を逃したときは、どう感じましたか。
「終わってよかった、という気持ち。芥川賞ともなると、会社の人の反応が全然ちがって、居心地が悪かったんです。『残念だったね』って慰められても、そもそもこれで世に出るとも思ってなかったので期待もしてなかったですし……。気まずい時間が早く過ぎてほしかったです」
新潮新人賞の受賞や芥川賞のノミネートによって書くものに変化はありましたか。
「芥川賞の選評で川上弘美さんが『できることをやっていては人の心を打てない』とおっしゃっていたのですが、中原中也賞に落ちたときに『優れていることが判断基準だったら竹中さんが受賞者だった』と言われたことがあって、それに近いなって。ほんとに文芸は難しい。『できないこと』を頑張っても、書き終われば『できたこと』になってしまう。でも、これって自分が書きにくいラインに来た時に避けずに突っ込めよ、ということだと思うんです。詰まった時は正解の方向に向かっているってことだ、と思えるようになって、以前より慌てなくなりました」
今後は小説とどう向き合っていきますか。詩や短歌も続けるのでしょうか。
「私にとって、この3つは3つとも同じ熱量で書きたいものなんです。だからこれからも小説も詩も短歌も書いていきたい。けれど、さすがに時間が足りなくて、会社の仕事をボリュームダウンできないものか、というのが目下の悩みです」
新人賞受賞後、竹中さんはすでに2作、小説を発表されています(新潮2025年6月号掲載の「水辺のフリスビー」、文藝2025年夏季号掲載の「骨折」)。2作目がなかなか出せない人もいるなか、そして残業アリの仕事を続けながら、異例のスピードです。
「角川短歌賞のときの教訓から、受賞後も考えすぎずガンガン行くしかないと思って。半年に1作は発表する、というのが今の目標です。数は裏切らないので」
竹中さんにとって「小説家になる」とは。
「今までとの違いは、締め切りを守る責任が生まれたってことくらい。高校の頃に抱いた『物書きになりたい』という夢は浮ついた気持ちからだったのですが、新人賞をとっても人生は変わらないと気づいた今は、ただ書きたくて書いています。すんごく忙しいけれど、書くのが楽しいんです」
【次号予告】永井荷風新人賞を受賞した春野礼奈さんが登場予定。市川沙央さんによる特別版も進行中。