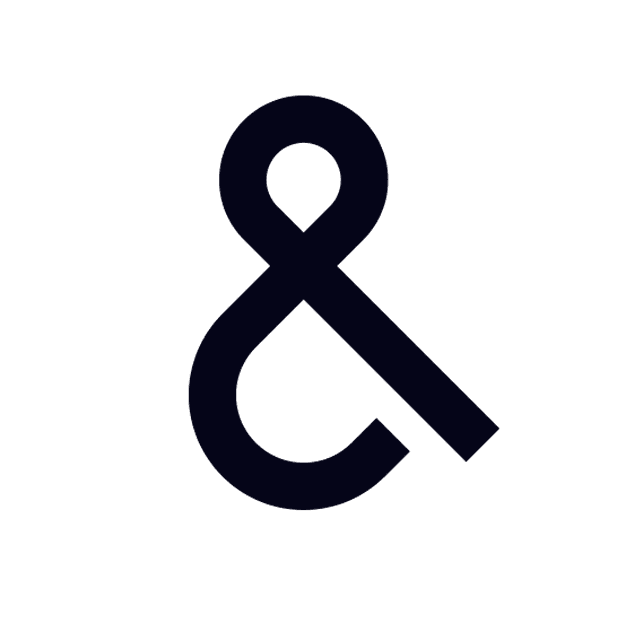フリーアナウンサーの宇賀なつみさんは、じつは旅が大好き。見知らぬ街に身を置いて、移ろう心をありのままにつづる連載「わたしには旅をさせよ」をお届けします。今回の旅はポルトガル。ヨーロッパの最西端で、大航海時代の人々について考えました。
「海の向こうに リスボン」
何度訪れても、ヨーロッパの街並みに慣れることはない。
中世を思わせるような石畳や教会、赤い屋根の家々。
日本にはない、絵に描かれたような統一感に心が躍る。
夏の終わりに、初めてリスボンを訪れた。
ヨーロッパ大陸の最西端。
大航海時代に世界貿易の中心となった街は、
今も世界中からやって来る観光客でにぎわっていた。
歩き始めて、すぐに気がついた。
とにかく、傾斜のきつい坂が多い。
青いワンピースに合うからと、白いパンプスを履いてみたものの、
気をつけないと滑ってしまいそうだった。
地図上では、すぐ近くにあると思った展望台にも、
なかなかたどりつかない。
トラムやケーブルカーが市民の足になっているのも、納得だった。
途中で、行列のできている店を見つけた。
周りには、サンドイッチのようなものを食べている人たちがいる。
ちょうどおなかが空いていたので、並んでみることにした。
注文してすぐに渡されたのは、
豚の薄切り肉を煮込んでパンに挟んだ、ビファナというポルトガルの国民食。
柔らかいお肉にはしっかり味が染み込んでいて、
煮汁が染み込んだパンとの相性は抜群。
かなりニンニクが効いているけれど、
日本のショウガ焼きを思い出すような、優しい甘さもあった。
そこからまたさらに歩いて、
リスボンの街とテージョ川を眺められる展望台にたどり着いた。
青色のタイルと、ピンク色の花のグラデーションが美しく、
写真を撮るには絶好のスポットになっているようだった。
この川を下れば、すぐに大西洋。
もちろん電気もなく、テクノロジーとは無縁の時代に、
大海原へ繰り出した冒険家たちは、何を思っていたのだろうか?
「最初に日本へ行った西洋人は、ポルトガル人だからね!」
展望台のカフェで、店員が教えてくれた。
そういえば、そうだったかもしれない。
教科書で習っていたはずなのに、すっかり忘れてしまっていた。
「だから、ポルトガル語と日本語は似ているんだ」
「オブリガート! アリガート!」
彼は誇らしげに笑った。
言われてみれば、確かにそうだ。
調べてみると、パンやボタン、カルタ、タバコ、天ぷらなど、
ポルトガル語由来のカタカナ語が、かなり多く存在している。
今から約500年前。
こんな遠く離れた場所から海に出て、アジアを目指した人たちが、
ほんの少し近くに感じられて、うれしくなった。
そのまま、空の色が変わりはじめるまで、
ゆっくりとサングリアを楽しんだ。
リスボンは夜になっても人通りが多く、危険な雰囲気がない。
夕食の後、もう一軒どこかに立ち寄りたいと思って歩いていると、
看板の「Fado(ファド)」という文字に気がついた。
ファドは、リスボンの下町で生まれた大衆音楽。
一度聴いてみたいと思っていたので、入ってみることにする。
ワインを一杯注文すれば、目の前で歌ってくれるカジュアルな店だった。
ポロシャツにスニーカーというラフな格好の男性が、
ポケットに手を突っ込んだまま前に出て、急に歌い出した。
コロンとした丸いギターが奏でる音色と、
よく響く情熱的な歌声に、胸が締め付けられそうになる。
もちろん歌詞の意味はわからないけれど、
悲しい歌なのだろうということは、すぐにわかった。
航海へと旅立つ大切な人との別れは、
この街の人たちにとって、日常だったのだろう。
次の日には、また別の街へ移動することになっていた。
偶然の出会いを楽しみ、別れを潔く受け入れる。
冒険を愛する者にとって大切なことは、ずっと変わらない。
「この海の向こうに、何があるのだろう?」
そんな好奇心が枯れない限り、私もまだ見ぬ世界を目指そう。