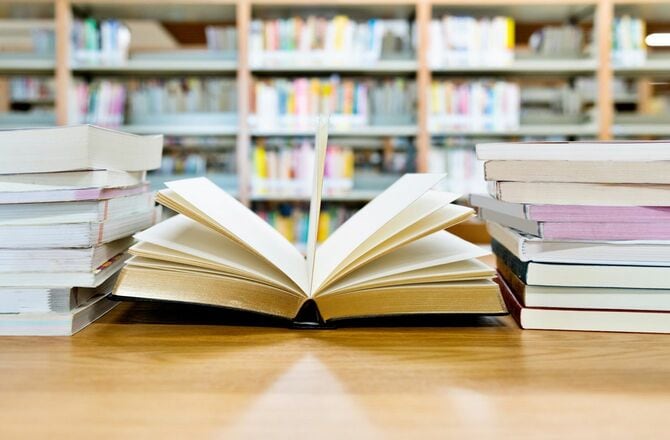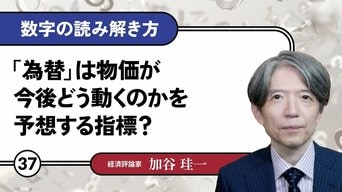※本稿は、佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』(Hanada新書)の一部を再編集したものです。
「知の巨人」が読んでいる高校の教科書とは
新しい知識を身に付けるのは難しくとも、過去に学んだあと眠っている記憶を呼び覚ますことは比較的に容易だ。そのためには、高校の教科書や参考書を再読し、時間を見つけてはチェックすることも重要だ。
最初に取り組むべきは「国語」。現代国語の教科書には、文学はもちろん、歴史や哲学といった文科系の文章から、物理や生物などの科学者の論文まで、幅広く載っている。現代国語の教科書自体がリベラルアーツの集大成だと言えるだろう。
次は「数学」。いまさら数学など、何の役に立つのかと思うかもしれない。しかし数学は、論理的な思考を育むのに必要不可欠な学問なのだ。
世界の超エリートは、文系学生でも「偏微分」など、日本の理系大学生レベルの数学を理解している。というのも、最先端の経済学では、数学の知識が不可欠になっているからだ。
もちろん定年後に、そこまで学ぶ必要はないのだが、二次方程式、因数分解、統計などの「数学I・A」レベルが理解できると、論理的思考力が格段に高まる。
さらに学びたいのが「倫理」だ。世界中の思想家、哲学者、宗教家の考えを知ることができるので、思考の鋳型を作ることができる。
社会人にいま本当に必要な学びは「倫理」
倫理は一見、実社会では役に立ちそうもないと見えるかもしれない。しかし、たとえばロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・パレスチナ紛争などの国際情勢を考えるとき、宗教や思想についての知識が大いに役立つ。
その国を動かすキーマンはキリスト教徒なのか仏教徒なのか、左翼思想の持ち主なのか右翼思想の持ち主なのか、現実主義者なのか理想主義者なのか……このとき様々な思考の鋳型を知っておけば、その行動原理が理解できる。そうして、当事者たちの動機が理解できれば、国際情勢を分析するのが容易になる。
これは国際情勢に限ったことではなく、対人関係にも応用できる。相手の考え方や行動の根本には、どんな思想や哲学があるのか――それを知ることができれば、人間関係も円滑になる。
高校の倫理の教科書や参考書は非常に完成度が高いので、詳しく学ぶことができる。特に山川出版社から出ている「もういちど読む」シリーズの『もういちど読む 山川倫理』を勧めたい。
この山川のシリーズは、ほかの教科書も秀逸だ。余裕があったら、『もういちど読む 山川世界史』『もういちど読む 山川地理』も読むべきだろう。
また理数系の本として勧めたいのは、講談社の「ブルーバックス」シリーズに収蔵されている『素数入門 計算しながら理解できる』『数論入門 証明を理解しながら学べる』だ。とても理解しやすいうえに、内容が面白い。