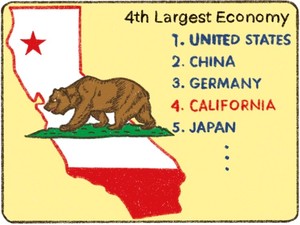ベルトコンベヤーで運ばれてきたおにぎりは、きれいで均一な三角形をしている。でも、ご飯からは「和牛焼肉」の具が少しあふれている。ほかにも、えびマヨネーズ、うなぎのかば焼き、鶏つくねなど、いろんな味のおにぎりがある。
ここは北京にある「北京旺洋食品」の工場。北京や天津、河北省地区にあるセブンイレブンに並ぶお弁当やおにぎりなどの商品開発、製造を担っている。
「日本品質」にこだわりながら、現地の習慣や好みに合わせた商品開発をしてきた。おにぎりの具がはみ出すくらい多いのも、「具量を重視」の好みによるものだ。
「挑戦的」な新商品も
そんな中、今年6月に、かなり「挑戦的」な新商品が出た。日本ではおなじみの塩むすびだ。
使ったのは、東北部黒竜江省のブランド米「五常大米」。中国にも、日本米と同じ短粒種で、「コシヒカリ」のようなブランド米がある。五常大米は特に有名で、香り高く、柔らかい食感が特徴だ。
SNS上では「他の米と違う。おいしい」といった声もあったが、売れ行きの状況を踏まえ、現在は販売を終了している。北京旺洋食品の中島幸造社長は「ご飯だけに価値を感じてもらうのはやはり難しかった」と話す。
だが、こうした商品が出るのは、中国の米の評判の高さを反映している。塩むすび以外のおにぎりも、東北部で生産された日本米に似ているという「東北米」を使っている。中島によると、日本米と「遜色のないおいしさ」という。
日本から米を輸出した場合、こんな中国産の米が、ライバルになる。
中国では、とうもろこしや小麦なども主食となるが、人口の6割が米を主食とする。主に南部で長粒種が、北部は日本米と同じ短粒種が生産されている。生産量は6対4で長粒種が多い。長粒種はパラパラと炊き上がるのでチャーハンに使われ、米粉の麺にも使われる。一方で、短粒種の東北米が「おいしい」という認識は全国で共有されているようだ。
質の高い米が東北部で作られる背景には、1910年の韓国併合以降、朝鮮半島からの多くの移民が東北部で水田開発し、旧満州国時代に日本が品種改良をしたことなどがあるという説が日中の専門家らの間で広まっている。
米の国際コンクールで健闘
その後の中国の米の質の向上については、品種改良や栽培技術の研究、農業機械購入への補助金といった生産者を下支えする政策の影響などが指摘される。
加えて、「世界一おいしい米を」という生産者や企業の熱意を要因にあげたのは、「米・食味鑑定士協会」の鈴木秀之会長だ。協会では中国の米も出品される国際大会「米・食味分析鑑定コンクール」を毎年、日本で開催している。
「金賞」は、日本の米ばかりだが、中国の米も健闘している。昨年、特別優秀賞を受賞した黒竜江省の企業は、中国の米は「日本のいい米とはまだ差がある」としつつ、「日本の米と十分に戦えるものもある」と話す。同じく特別優秀賞を取った内モンゴルの企業は、おいしさだけなら「10年以内に日本を超える」と強気だ。
米国農務省のデータによると、過去5年の中国の米生産量は年平均で約1億4600万トン、消費量は24~25年は約1億4500万トンで、ともに世界最多だ。ただ、人口減少や主食の多様化などで需給のミスマッチが起きているとも指摘される。
食糧関連の専門紙は、近年の不動産不況で建設作業員が減り、AIの使用や自動化により工場労働者が減ったことも需要の低下に影響していると分析。米をたくさん食べる「力仕事」をする人が減ったという見方だ。一方で、現地メディアが伝えた専門家の分析によると、質の高い米の需要は高い。米不足にならない「絶対安全」を保つため、輸出には現時点で積極的ではないという。
米農務省によると、中国の24~25年の輸入量は約233万トン。日本の財務省によると、日本からも24年に172トンを輸入した。
日本からの米輸出には条件
ただ、日本からの輸出には壁がある。
中国の検疫条件により、中国側が認可した施設で精米し、害虫などを駆除するため「くん蒸」をしなければならない。精米して1~2カ月がおいしく食べられる期間と言われる。中国への日本米の輸出を手がける日本の専門商社「板橋貿易」によると、これらの作業を経て消費者に届くのには3カ月ほどかかり、「味は多少落ちてしまう」。
予想外のリスクもある。同社は13年から輸出を始めたが、23年に福島第一原発の処理水が放出されると、現地の日本食料理店が相次いで閉店。輸出量もピーク時の3分の1以上落ち込んだという。いまも、福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野の米を含む農産物の輸入が規制されている。
価格面の課題も大きい。生産者や商社など100社でつくる「全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会」によると、日本米は輸送コストもあり、1キロ70元(約1400円)~100元(約2000円)。中国の米の値段の平均より、約4倍も高いという。
日本からの輸出に活路はあるのか。中国の米事情に詳しい日本水稲品質・食味研究会の松江勇次会長は「富裕層向けに有機栽培の米などを『安心・安全』で売っていくべきだ」と強調する。
また、日本食人気は根強く、日系の回転ずしチェーンは好調だ。板橋貿易の担当者は「厳しいが、日本産にこだわる店もある。市場はまだあるはずだ」と話す。