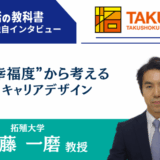「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「デジタルハリウッド大学でのキャリア教育の取り組み」や「就活で大切にすべき考え方」について知ることができます。
「就活の教科書」編集部小林
尾方先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
尾方僚 特任准教授
尾方 僚(おがた・りょう)
デジタルハリウッド大学 特任准教授
上智大学文学部(現・総合人間科学部)社会学科卒業後、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(KBS)アントレプレナースクールで学ぶ。文化放送ブレーンで広報・マーケティングを担当した後に独立し、採用コンサルティングや学生向けキャリア教育プログラムを開発。大学のキャリア教育単位化授業開始当初から実務家教員として携わり、日本女子大学、日本工業大学などでキャリア形成科目を担当。
現在は新卒だけでなく、社会人のリスキリング・リカレント教育、またグローバルキャリアにも注力。日本女子大学リカレント教育課程では働く女性のためのコースを担当。コロナ禍で大学がオンライン授業に切り替わった際にハイブリッド授業への挑戦をエッセイ漫画で発表し、大きな話題を集めた。キャリアデザイン学会所属(現在学会代議員)
→https://note.com/dhu/n/n7a95acf71294
→https://www.buzzfeed.com/jp/reonahisamatsu/onlineishard?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfshareemail
→https://msl.dhw.ac.jp/wp-content/uploads/2024/12/DHUJOURNAL2024_P059.pdf
目次
デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授にインタビュー①:「キャリア教育」とは?
キャリア教育の始まり
「就活の教科書」編集部小林
さっそくですが、尾方先生にとってキャリア教育とはどのようなものでしょうか?
教員を始めたのは日本女子大学で、きっかけはキャリア形成科目の設置です。
文部科学省が大学にもキャリア教育を推進しようという流れになっていますが、その少し前から私は関わっていました。
実は“インターンシップ”という言葉を日本に持ち込んだのも、大学院でのビジネスプランからなんです。
当時はまだ学生を受け入れる企業も少なく、マナーができていない学生を送り出すと『使えない』と言われてしまう。
そこで専門学校と組んで、基礎的なビジネス教育を始めたんです。
その後、金融を中心とする外資系企業の日本の大学生(新卒)の採用ブームが来て、面接官のトレーニングや、アメリカのコンピテンシー評価を日本の学生向けにアレンジする仕事を多く手がけました。
採用側の仕事も徹底的にやったのですね。またインターンシップ先駆者事例として東京都の委員などもつとめました。
そうした実績から、日本女子大学の教授に声をかけてもらい、『社会に出るための自己表現』という授業を始めたのが最初です。
それから日本工業大学やデジタルハリウッド大学でも教えるようになり、気がつけばもう20年近く続けていますね。
ね。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育が日本で始まった頃から携わってらっしゃるのですね…!
リスキリング・リカレント教育:学び直すことで、自分のキャリアを再構築する
「就活の教科書」編集部小林
先生の研究テーマにもある「リスキリング・リカレント教育」について教えてください!
社会に出ると壁にぶつかることが多いんです。
就活で『受かったからこの会社に入ったけど合わなかった』や、女性が管理職になったときに『男性向けの研修に違和感がある』といった壁にぶつかることがあります。
そういうときに“リスキリング・リカレント教育”が大事になってきます。
学び直すことで視点を切り替えたり、自分のキャリアを再構築したりできるんです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
リスキリング・リカレント教育は、“学び直す”ことで困難を乗り越えるためのものなのですね!
仕事は“インプットとアウトプットの繰り返し”
仕事はアウトプットが中心ですが、インプットがなければ枯渇してしまいます。
だからこそ、“インプットとアウトプットの繰り返し”が必要なんです。
私自身も大学院に通って学び直しを経験し、多くを吸収しました。
その経験から、今はリカレント・リスキリングを自分の大きなテーマとして取り組んでいます。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
“学んだことをアウトプットし、アウトプットしたことからまた学ぶ”のが仕事において大事なのですね!
デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授にインタビュー②:大学でのキャリア教育の特徴
キャリア教育が1年生から必修
「就活の教科書」編集部小林
デジタルハリウッド大学では、どのようなキャリア教育の特徴がありますか?
デジタルハリウッド大学は、日本で唯一“株式会社が運営している、通学制の大学”なんです。
先日は文部科学省 令和7年度「数理・データサイエンス・AI教育プログラム リテラシーレベル プラス」に認定されました。
特徴的なのは、キャリアデザインを1年生の必修にしているところですね。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
株式会社が運営してる大学なのですね…!
どのような学生が多いのでしょうか?
学生の多くは“クリエイターになりたい”と夢を持って入学してきます。
でも、入学後に天才的にできる学生を目の当たりにして、自分の立ち位置を見失ってしまう子も多いんです。
そこで、『創れることだけが全てじゃない』と伝えるようにしています。
例えば、企画をまとめるマネジメント力や、人を動かす力も大事なキャリアの一部です。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
専門性が高い大学だからこそ、躓いた時に悩んでしまう学生もいるのですね。
授業では、面接や社会で本当に求められる“人間力”を磨いていく
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育の授業で大切にされていることは何ですか?
キャリアデザインの授業で大切なのは、ハードスキルだけでは足りないということです。
たとえばゲーム会社の採用ページを見ると、デザイナー職であっても“共感できるデザインを作るには、デザイン力だけでなくコミュニケーション力も必要”と書かれています。
デザイン力(=ハードスキル)は専門の先生が教えてくれますが、私の授業では“コミュニケーション力”の部分を徹底的に鍛えます。
授業ではディスカッションを重ねたり、ポスターを作って発表したりと、アウトプットや表現力、実行力を育てるトレーニングをしています。
つまり、社会で本当に求められる“人間力”を磨いていくんです。。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
目先の就活テクニックにとらわれてしまいがちですが、本当に大切なのはコミュニケーション力をはじめとした人間力なんですね。
キャリアとは“その人の生き様”
よく学生には、美術館に行かせるようにしています。
美術館に行くと“天使と悪魔が戦っている絵”なんてたくさんあるでしょう。
学生にそれを見せて『先人たちも同じようなことを考えてそれを具現化してきたわけだよね』と伝えるんです。
キャリア教育は、単なるハードスキルを教えるだけじゃないんですよ。
スタンフォード大学の教授であるクラン・ボルツ理論”というものがあります。
これは『キャリアとは偶然の積み重ね』という考え方なんです。大事なのは、その偶然をどう引き寄せるか。
そしてもう一つ、キャリアとは“その人の生き様”でもあるということです。
だから“就職はゴールじゃない”。起業する人もいれば、一度どこかで修業してから新しい道に進む人もいる。
実際、デジタルハリウッド大学の卒業生の中には、米国アカデミーが主催する学生版オスカー「学生アカデミー賞」で日本初の受賞をした学生もいるんですよ。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
アカデミー賞を取った学生がいるなんてすごいですね!
デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授にインタビュー③:実践的な取り組み
3日間のオンライン合宿:具体的なキャリアイメージを描く
「就活の教科書」編集部小林
いざ就職活動を始めたときに「何をしたらいいかわからない」という学生はたくさんいると思います。
そのような学生に対して、取り組まれていることはありますか?
デジタルハリウッド大学ならではの“3日間のオンライン合宿”を行います。
『アニメに関わる仕事がしたい!』と思っても、実際には職種がたくさんあって、学生は何を目指せばいいのか分からないことが多いんです。
そこで、実際に業界で働いている先輩たちに来てもらい、OB・OG訪問のように話を聞ける企画をしています。
具体的なキャリアイメージを描けるようになるのが狙いです。
尾方僚 特任准教授
就活に必要な流れを一通り体験できる
「就活の教科書」編集部小林
オンライン合宿とは面白そうですね!
どんなことをするのでしょうか?
この合宿は完全オンラインで、就活に必要な流れを一通り体験できるようになっています。
まずは企業研究のやり方を学び、OB・OG訪問では実際に先輩たちがオンラインに来てくれて、ブレイクアウトルームに分かれて話を聞けます。自分でアポイントを取らなくても先輩を訪問できるんです。
それから、自己PR動画の撮り方を動画の先生に教わります。
次の日はガクチカや自己分析のワーク、ビジネスマナー、模擬面接からフィードバックと進んでいきます。私も講座を担当します。
さらに、ポートフォリオ(作品集)の作り方講座や、就活でつまずきやすい筆記試験対策(SPIや簿記)、グループディスカッション練習も行います。
最後は自分たちで準備したプレゼンを発表して、打ち上げで締めるんです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
就活準備で必要なものが網羅されてますね…!
3日間の合宿は、まさに“就活のチュートリアル”です。
自己PR動画の作成から面接練習、グループディスカッションまで、就活の一通りの流れをオンラインで体験できます。
OB・OG訪問も組み込まれているので、就活に必要な準備を短期間で網羅できるんです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
OB・OG訪問ってなかなかハードルが高いんですが、それもできるなんて羨ましいです!
いろんなキャリアのロールモデルに出会える
就活生の多くは『先輩にどう連絡したらいいんだろう…』と躊躇してしまいます。
でも、この合宿では先輩たちが直接オンラインで来てくれるので安心です。
しかも業界は多彩で、アニメやエンタメだけでなく、銀行や広告代理店、エアライン、起業家、また企業で人事担当をしている先輩もいます。
色んなキャリアのロールモデルに出会えるのが大きな魅力です。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
先輩たちが来てくれる上に、いろんな業界で働いている人の話が聞けるなんてすごいですね!
デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授にインタビュー④:就活における誤解
就活に対する甘い認識
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育の授業を通して、学生からはどのような印象を受けますか?
1年生のうちは、まだ就活の大変さが分かってないんですよね。
『自分はCGを勉強しに来たのに、なんでディスカッションやプレゼンが必要なんだろう?』って思う学生も多い。
でも3年生くらいになると、『あの授業、役に立った!』と気づきます。
実際、面接のない会社はありませんから、本当は早いうちから準備が必要なんです。コミュニケーションスキルは今日明日で一気にあがることはないわけで日ごろからの積み重ねですからね。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
1年生のうちはなかなか実感がないですが、いざ就活を始めてみると準備の大切さがわかりますよね…
企業は“欲しい人材”がいなければ採用しない
「就活の教科書」編集部小林
「就活の大変さ」としてどのようなことが挙げられますか?
「今は人手不足だから就職は簡単だろう」と思っている人もいますが、それは大間違いです。
企業は“欲しい人材”がいなければ採用しません。
むしろ待遇が上がるほど、厳しく選びます。だから希望すれば誰でも入れるわけではない。
志望企業によっては倍率が何百倍、何千倍にもなることを理解しておいた方がいいのです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
「人手不足だからまあ大丈夫かな」と私も甘く考えてしまっているところがあったので気をつけたいです…
よく学生に「親戚にアラブの王様いる?」って聞くんです。大抵いないですよね。
でも王様だって生活を維持するために働いている。投資家だって、毎日必死に数字と向き合ってる。
つまり“遊んで暮らす”なんてできないんです。
大学生の特権は“勉強に専念できる時間”であって、働くのは全く別物。
企業は利益を上げるために“人材”を求めている。
だから就活も成績だけじゃなく、コミュニケーション力やプレゼン力など別の能力が必要なんです。
面接官も学生を落としたいんじゃなくて、“利益を生み出せる人”に会いたいんですよ。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
“楽に見える仕事”に憧れてしまいがちですが、実際にはそんな仕事はないんですよね。
企業が知りたいのは“あなたがどう活躍するか”、自分なりのネタを掘り下げる
「就活の教科書」編集部小林
企業は学生を面接する際に、どのような部分を見ているのでしょうか?
学生がよく言う「世のため人のために働きたい」は、企業には響きません。
利益を出して税金を納め、社員に給料を払っている会社はすでに社会に貢献しているんですから。
志望動機に必要なのは“きっかけ”ではありません。
企業が知りたいのは、『あなたがこの会社でどう活躍して、利益を生み出してくれるのか』ということです。
そこを理解しないと、就活はうまくいかないんです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
志望動機を書くときに、いつも“きっかけ”ばかり書いてしまっていましたが、企業が求めている本質とは違うのですね…
就活でよく自己PRを書く、話したりすることが多いですが、自己PRのポイントはありますか?
例えばある授業で自己PRを2分間発表させると、35人のうち半分以上がカフェなどの“アルバイト経験”を語るんです。
最初はみんな自信満々で語るのですが、同じ内容が続くと『埋もれるんだな』と気づく。
だから大事なのは“自分なりのネタ”を掘り下げること。『お客様目線で工夫した』は誰でも言えます。
そうではなく「お客様目線で工夫したことは具体的に何なのか」また、インターン経験を自己PRのネタにするならf「インターンで自分がどう貢献したか、どんな成果を残したか」そこまで具体的に考えて自己PRにする方が、確実に差別化できます。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
よく使われる言葉は便利ですが、その分埋もれてしまうので、自分なりの経験を言葉にした方が響きやすいですよね!
デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授にインタビュー⑤:就活におけるポイント
就活は自分が“納得できる選択”を
「就活の教科書」編集部小林
就活において、大事にするべきことは何でしょうか?
どんな進路を選んでもいいんですが、大事なのは“自分が納得して選ぶこと”です。
『受かったからここでいいや』ではなく、自分の価値観に合う場所を探してほしい。
会社に限らず、公務員や他の道でも構いません。とにかく逃げの選択はやめて、自分なりのモノサシを持つことが就活では大切なんです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
内定を取ることばかり考えてしまって、自分の価値観に合わない会社に入るのは意味がないですよね。
「好きだから」だけでは通用しない:企業が求めているのは“ファンを増やせる人”
また、旅行が好きだから旅行代理店、というのは“お金が好きだから銀行”と言うのと同じで成り立ちません。
企業が求めているのは“商品やサービスのファンを増やせる人”なんです。
だから「この会社が大好き」という気持ちだけで臨むと、落ちたときに立ち直れなくなる。
大事なのは「好きだから働きたい」ではなく、「自分の力でこの会社のまたは製品のファンをもっと増やしたい」と示すことです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
「好き」だけで突っ走ってしまうのも良くないのですね…!
日本の就活は、業界のトップ企業を回れる最高のチャンス
日本の新卒就活は世界的に見ても珍しいシステムで、同じ時期にあらゆる業界のトップ企業を回れる最高のチャンスです。
社会人になったらできない経験ですから、この機会を無駄にしないでください。
もし『自分は給料重視だ』と思うなら、それで構いません。
お金も大事な価値観のひとつですから、高給の会社を目指せばいいんです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
就活も貴重なチャンスと考えて、前向きに取り組んでいきたいですね!
デジタルハリウッド大学 尾方僚 特任准教授から学生へのメッセージ:「キャリアは偶然の積み重ね。旅を楽しんで欲しい。」
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございます!
最後に、学生へのメッセージをお願いします!
私自身も大学の先生になるなんて思ってもいませんでした。キャリアは“偶然の積み重ね”なんです。
ただし、その偶然は待っていてもやってこない。
自分で動いて掴みに行くことが大切です。できるだけ多くの“偶然”を掴んでほしいと思います。
就活には皆さん一人ひとりに正解があるので、自分の正解を探す旅だと考えてください。
その旅をぜひ楽しんでほしいです。
尾方僚 特任准教授
「就活の教科書」編集部小林
素敵なメッセージをありがとうございます。
尾方先生、本日は本当にありがとうございました!