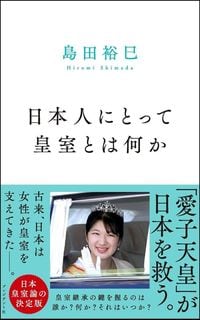政子と兼子が日本の国を完成に導いた
鎌倉幕府を立ち上げたのは源頼朝だが、頼朝が亡くなった後、権勢をふるったのはその妻である北条政子であった。政子は夫の死後出家しており、「尼将軍」として幕府の政治を実際に動かした。
一方、同じ時代に朝廷で権勢をふるったのが「卿局」と呼ばれた藤原兼子だった。兼子の父親であった藤原範兼は司法全体を管轄する刑部卿で、卿局の名はそのことに由来する。兼子は後鳥羽天皇の乳母として重んじられ、院政に介入した。鎌倉幕府の第3代将軍源実朝が暗殺された後、兼子は政子に対して冷泉宮頼仁親王を将軍に推している。
慈円は、政子と兼子が権勢をふるうようになったことを指して、女人入眼の日本国がいよいよ本当のことになった、女性が日本の国を完成に導いたと指摘したわけである。
それに続いた人物もいた。それは、拙著『日本人にとって皇室とは何か』(プレジデント社)でも触れたが、室町時代から戦国時代初期に摂政関白太政大臣を務めた一条兼良も、女性が日本の国を治めることが本来のあり方だという指摘を行っていた。
「日本は女性が治めるべき国である」と記した一条兼良
藤原家は、藤原不比等の4人の子どもによって、北家、南家、式家、京家に分かれたが、北家の嫡流が九条家で、一条家はその庶流だった。兼良は政治家であるとともに学者で、同時代の人々からは「日本無双の才人」と評価され、自身も菅原道真以上の学者であると自認していた。相当の自信家だったようだ。
つまり彼は日本の歴史に深く通じていたわけで、室町幕府の第9代将軍足利義尚に求められて書いた『樵談治要』という書物の中で、「日本は女性が治めるべき国である」と述べていた。
中国では、日本のことを「姫氏国」と呼ぶことがあった。それは、周王朝で「姫」という姓が用いられ、その分家である呉王も同じく姫を姓とし、その末裔が倭の人々とされたからである。ただし、そこで言われる姫とはお姫様のことではない。
ところが、兼良は、この姫氏国を女性が治める国と解釈した。これは間違った解釈になるが、根拠はあった。根拠となるのは、皇室の祖神がアマテラスという女神であること、神功皇后が69年にもわたって治世を担ったこと、そして、飛鳥・奈良時代に女性天皇が続出したことなどである。