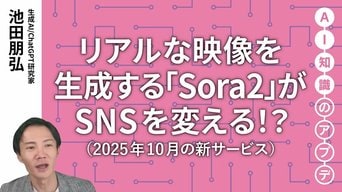高齢者の医療の負担はどうあるべきなのか。実業家の堀江貴文さんは「血圧や血液検査など、治療可能な疾患を見つけることのできる検査は続けるべきだ。一方で、日本には何の意味もない検診に税金が使われ続けている実態がある」という――。
※本稿は、堀江貴文著、予防医療普及協会監修『日本医療再生計画 国民医療費50兆円時代への提言22』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
医療の進歩がもたらした「過剰診断」という皮肉
私は最近、ある衝撃的なデータを見た。75歳以上の乳がん検診では、約47%が「過剰診断」になる可能性がある。さらに85歳以上では、実に50%を超えるのだという。
過剰診断とは何か。簡単に言えば、その人が生きている間に症状も出ないし、死因にもならないような病気を見つけてしまうことだ。そして、見つかった以上は治療することになる。手術、抗がん剤、放射線治療。これらは高齢者の体に大きな負担をかけ、かえって生活の質を低下させる。
これは医療の進歩がもたらした皮肉な結果だと私は思う。検査技術が向上し、小さな異常も見つけられるようになった。しかし、それが本当に治療すべきものなのか、それを考えないといけない。
世界は75歳以上に「がん検診」を推奨していない
興味深いことに、先進国の多くが高齢者の積極的な検診には慎重になっている。
カナダでは75歳以上の大腸がん検診を非推奨としている。アメリカでも85歳以上には推奨していない。イギリスのNHS Health Checkは74歳で終了だ。
なぜか。答えは単純で、死亡率低下に資するかといったことや延命効果についての科学的根拠に乏しいからだ。75歳以上の高齢者に対するがん検診の効果を示すランダム化比較試験は、ほとんど存在しない。
つまり、検診が本当に命を救っているのか、誰も証明できていないのだ。
一方で、過剰診断のリスクは年齢とともに確実に上昇する。余命が限られている人に、10年後に問題になるかもしれない小さながんを見つけて、今すぐ治療する意味があるのだろうか。