抹茶が世界的ブーム 古くからの宇治の茶商は需要急増にどう対応
ヘンリー・リッジウェル BBCポーランド語
京都府宇治市にある中村藤吉本店の前には、猛暑の中でも、早朝から行列ができ始める。宇治は多くの人にとって、抹茶の心の故郷だ。
鮮やかな緑色の抹茶は、うま味豊かなその味わいに加え、健康効果があるとされることから評価され、今や世界的なブームとなっている。
熱心な抹茶ファンは、究極の目的地として宇治を目指す。しかし地元の抹茶生産者は、需要に供給が追いつかず、抹茶が品薄だと心配する。

Z世代
中村藤吉本店は宇治市の中心に店を170年間構え、皇室にも茶を納めてきた。宇治には同じように、古くからの茶商が複数ある。
伝統的に、最高品質の抹茶は湯で点(た)て、やや苦味のある茶にし、茶事や茶席で出される。
日本国内では長年、抹茶の販売量は減少傾向にある。今では、その半分以上が海外に輸出されている。
そして、宇治の茶商を新しく訪れるようになった典型的な客は、これまでの客層とは大きく違う。新しい客たちは若く、国際的で、最高の抹茶に惜しみなくお金を使い、ソーシャルメディアに投稿するような人たちだ。
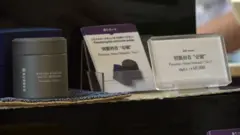
世界的な抹茶ブームは、抹茶を食材として使うことで、加速している。飲み物、アイスクリーム、ケーキ、ラーメンなどなどだ。抹茶を使ったレシピは、ソーシャルメディアで次々と拡散され、熱心なフォロワーによってますます広まる。抹茶ラテは今では、世界中のコーヒーチェーンの定番メニューだ。
抹茶に熱狂
中村藤吉本店の中庭は、黒松の古木が影を落とす、静かな日本庭園だ。
その静寂は午前10時ちょうど、茶店が開店すると同時に破られる。
客は、数十缶しかない30グラムあたり6000円余りの高級抹茶を求めて殺到する。スタッフは対応に追われる。
この店で一番高価な抹茶は、20グラムで6万円だ。
一番人気の抹茶は、数分のうちに売り切れる。完全な品切れを避けるため、1日あたりの販売量も制限されている。

画像提供, AFP via Getty Images
健康志向
カナダ・ケベック州から店を訪れていたバンジャマン・ジェルヴェさん(15)はこの日、早朝から並んでいた。家族と一緒に近くの京都市に来ていたので、宇治まで行こうと説得したのだという。
「ソーシャルメディアでこの店のことを知って、来てみたかったんです。すぐに売り切れると聞いたので、開店前に着いて、抹茶パウダーを手に入れました」とジェルヴェさんは話した。
「抹茶ラテを作るつもりです。味がとても好きだし、カフェインも入っているので、一日の活力をもらえます。それに、体にもけっこういいし、抗酸化作用もあるし、緑のものを毎日とるのにちょうどいい」
米テキサス州から来たというレシュマ・ジョゼさんにとっては、今回が2度目の宇治訪問だった。
「昨年ここに来たときは、あまりたくさん買わなかったんです。その後になって抹茶ブームがものすごいことになって、何もかも売り切れてしまった。だったら大元へ行こう、抹茶を買いに宇治へ行こうと思ったんです」
抹茶不足

画像提供, Getty Images
中村藤吉本店の7代目当主で、茶店とカフェを統括する中村省悟氏は、抹茶の需要に供給が追いつかないと心配している。
「今日も見ていただいたとおり、朝の2、30分で全部なくなってしまいますので、品薄かと言われたら、もうものすごく品薄です」
生産者によると、抹茶の製造工程は複雑で、世界的な需要急増に対応するのが難しいという。
抹茶の原料となる「碾茶(てんちゃ)」を栽培する茶畑の約25%は、宇治周辺の丘陵地にある。残りは日本の他の地域で作られる。
茶の木は一定期間、日陰でゆっくり育てられる。摘んだ葉を乾燥させた後、石臼で粉末にする。石臼では、1時間に約30〜40グラムしか抹茶を作れない。
「お茶の木を植えてから、実際にお茶の葉を収穫できるまでに最低でも5年かかるので、たとえばすごく需要が増えたからといって、今日言って明日いきなり増やすのはちょっと難しい」と、中村氏は言う。
気候変動

画像提供, Getty Images
日本はこの状況に対応しようとしている。農林水産省によると、抹茶の生産量は2010年以降ほぼ3倍に増え、年間4000トンを超えている。日本のメディアによると、政府は碾茶の栽培促進のため、農家向けインセンティブを計画している。
しかし、近年の猛暑を筆頭に、気候変動の影響が最近の収穫に打撃を与えている。日本の高齢化も、茶農家の減少につながっている。
日本が世界の抹茶需要になかなか応えられずに苦労する中で、世界的な抹茶人気が悪用されかねないと、中村氏は懸念している。
「何が抹茶なのかという基準がないので、中国でも作られたり、たとえば台湾でも作られたり、韓国でも作られたりしています。お茶の木は東アジア全体に広がっているので、要するにそれを粉にしてしまえば、何でも抹茶だっていう」
日本の抹茶業者は今のところは、世界的ブームを受け止めている。そして、抹茶ラテなどさまざまなレシピには、価格の比較的安いものを使うのがいいと推奨している。
他方、高級のワインやオリーブオイルと同じように、最高品質の抹茶はそのままお茶として味わった方がいいと抹茶の愛好家たちは言う。まるで日本の天皇のようにして。











